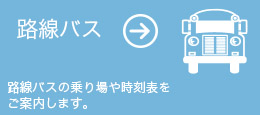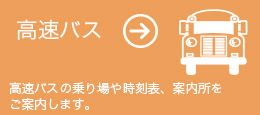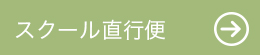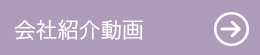運輸安全マネジメントに関する取組みについて
新常磐交通株式会社では、輸送の安全を確保するために、以下のとおり全社員が一丸となって取り組んでまいります。
1 輸送の安全に関する基本的な方針
(1) 取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、事業所における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現業部門の状況を十分に踏まえつつ、社員に対して輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
(2) 会社は、輸送の安全に関する「計画の策定、実行、チェック、改善(これを「Plan Do Check Act」という。PDCAチェック表による)」を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行するほか、絶えず輸送の安全の向上に努めてまいります。また、輸送の安全に関する情報については、公表いたします。
2 令和7年度 事故防止目標
ABCに取り組もう
運転に法令遵守のこころを
(ABC:当たり前のことを・バカにしないで・ちゃんとやる)
乗務前の完全チェック
◎アルコール検知器、運転免許証の確認、健康状態、適切な車両点検
運転時
◎制限速度ではなく、安全速度を優先、適切な車間距離の保持
◎「前方注視の義務」の徹底
◎確実な安全確認の励行
◎バス車内のスマホ・携帯電話・タブレット等の使用厳禁
①健康に起因する事故の防止
②車内事故の撲滅
③有責事故15件以内
※詳細は別添の当社事故防止目標の通り
3 事故統計
①自動車事故報告規則第2条に規定する事故
令和6年度 1件
②当社が規定する有責事故・無責事故件数
有責事故 27件 無責事故 40件 総件数 67件
(前年度 有責事故23件 無責事故34件 総件数57件)
4 輸送の安全に関する組織体制
別添 安全統括管理者組織図の通り
5 輸送の安全に関する重点施策
(1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令および安全管理規程に定められた事項を遵守いたします。
(2)輸送の安全の確保に関する費用支出および投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
(3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じます。
(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有いたします。
(5)輸送の安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施いたします。
6 輸送の安全に関する計画
(1)教育計画
年間計画を作成のうえ、全乗務員の運転状況を実査するとともに、運転者教育を行います。令和3年12月には、「教育指導課」を立ち上げ、全従業員に対する指導教育を一括で行います。また、新人運転者の指導教育についても、「班長制度」の下で行っておりましたが、「指導教育課新人研修担当係」を選任し、行うこととなりました。
本社部門が現地に出向いて、全事業所の運行管理状況等を把握のうえ指導を行います。
(2)設備投資
車両については、「車両委員会」を開催し老朽化等による事故を防止するため計画的に代替してまいります。
令和6年度においては、高車齢化車両について、低床式の中古車両で入れ替えを行ってまいります。
構内の後退時の事故防止策として、路線バス・高速バス・貸切バス全車両に「バックモニター注視」のステッカーを貼付し、全運転者に対して啓蒙策を行ってまいります。また、新たに導入する車両については前照灯と路肩灯をLED化して、視認性を高める継続的な取組みを行ってまいります。
令和5年度から6年度にかけて、運転者の負担軽減と車内事故防止の観点から、「バスロケーションシステム」と「地域連携ICカード(LOCOCA)」の運用を開始いたします。
(3)事故防止対策
社内に「事故防止対策委員会」を設け、2カ月に1回の割合で開催し事故防止対策を検討し、それを実施してきましたが、運輸安全マネジメント推進のための中心機関として、その運営に当たってまいります。
特に、過去の事故事例及びヒヤリハットの分析を行い、その後の事故防止対策と致します。
運転者からの情報により、危険個所のハザードマップの作成と、緊急時の迂回ルートの選定を行ってまいります。
更に、決定された事項を末端まで浸透させるよう、「班長制度」を発展的に解消し、「指導教育課新人研修担当係」を通じて、行ってまいります。
そのために、「指導教育課連絡会議(乗合部・総務部参加)」を通じて、安全に対する意識の醸成に努めてまいります。
また、春の全国交通安全運動(4月上旬)秋の全国交通安全運動(9月下旬)にあわせて事故防止運動を重点的に展開するほか、繁忙期の事故防止対策として夏期輸送の事故防止運動(7月中旬~8月末)ならびに年末年始輸送の安全輸送総点検(12月中旬~1月上旬)を実施するなど、年4回の交通安全運動を中心として輸送の安全性向上に努めてまいります。
また、健康に起因する事故を防止するため、全乗務員に対するSAS(睡眠時無呼吸症候群)検査および治療の必要な者については、治療の指示および推進を継続的に行ってまいります。
産業医の意見により、特定運転者を対象に脳ドックの導入を継続的に行ってまいります。
(4)安全統括管理者会議および統括運行管理者会議の開催
経営者レベルと現業部門の代表者による意見交換等を含めて会議を開催し、双方向で情報の共有化を実践のうえ輸送の安全性向上に努めます。
(5)貸切バス事業者安全性評価認定
令和6年度は、4回目の三ツ星認定を受け、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」において、高いレベルでの安全確保への取り組みを持続しております。
(6)感染症対策
感染症対応として、お客様・従業員の安全確保を第一に様々な対策を行います。
・マスク着用の励行、手の消毒と手洗い、うがい等の徹底
・運転者の出勤前検温の励行と点呼時の検温(非接触検温器の導入)
・オゾン発生装置の設置(高速バス・貸切バス全車両、一般路線バスの100%に設置済)
・バス車内の消毒と換気(一般路線バスは適宜、高速バスは最低2回)
・事務室、乗務員控室、乗車券売場、待合室等の定期的な換気及び消毒の励行
・ロッカールーム等、気密性の高い部屋での換気
・社屋に入る場合の手の消毒義務(営業所への啓蒙看板の設置)
・乗務員休憩室(一部)へのオゾン発生装置の設置
7 輸送の安全に関する予算等の実績額
輸送の安全性向上を目的として取り組んだ「各種工事等の改善」の金額は、下記のとおりです。
令和6年度車両・設備等の改善(新規購入、資本的支出) 287,468千円
8 事故・災害等に関する報告連絡体制
別添 緊急連絡体制図の通り
9 安全統括管理者
常務取締役 門馬 誠 (平成18年12月25日選任)
10 安全管理規程
別添 安全管理規程による
11 輸送の安全に関する教育および研修計画
(1) 経営トップと現業部門の代表者
経営者と現業部門の代表者が情報の共有化を図り実践のうえ輸送の安全性向上に努めるため、定期的に安全統括管理者会議および統括運行管理者会議を開催いたします。
(2)運行管理者関係
年2回以上、本社部門が現地に出向いて全事業所の運行管理状況等を把握のうえ指導を行います。
(3)運転者関係
年間計画を作成のうえ、全乗務員の運転状況を実査するとともに、事業所単位で運転者教育を行います。
また、年6回以上、本社部門が現地に出向いて、全事業所の運行管理状況等を把握のうえ指導を行います。
「運転者に対する指導、監督の指針」に基づき、全ての運行管理者、運行管理補助者、運転者、整備管理者に対し、教育を行います。
なお、この教育は一般管理部門の乗務員も対象として実施します。
12 内部監査の実施
全事業所の内部監査を実施し、監査結果を経営トップに報告のうえ安全上の問題事項については、改善に努めます。
13 一般貸切旅客自動車運送事業に関する情報
一般貸切旅客自動車運送事業に関する情報について(PDF)
14 初任運転者に対する安全運転の実技指導の公表について
「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項に基づき公表します。
初任運転者に対する安全運転の実技指導について(PDF)
15 行政処分の状況
(1)行政処分日 令和7年6月24日
(2)対象営業所 いわき中央営業所
(3)違反事実 道路運送法第25条・第27条3項・旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3